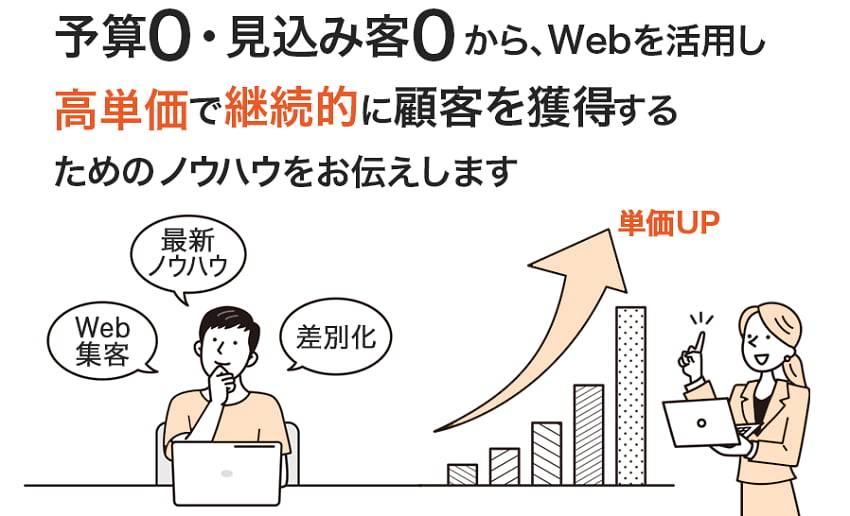伊藤耕一郎(いとうこういちろう)さんは、スピリチュアリティ研究の分野で多くの実績を持つ研究者です。
仕事の中心は執筆です。論文執筆や学会での発表、大学での教育が日常の一部となっているとのこと。
スピリチュアリティという言葉はしばしば誤解されがちですが、伊藤さんの研究は、心の奥底にある無意識の領域に焦点を当てています。それは「生きる意味」や「存在意義」といった哲学的な問いに対する深い探求です。
「私が手掛ける論文は、スピリチュアリティに関連するものがほとんどです」と話してくれた伊藤さん。
スピリチュアリティとの出会いと現在の活動内容、志師塾で得られたこと、今後のビジョンについてお話をうかがいました。
1.スピリチュアリティとの出会いと社会貢献
1.1 スピリチュアリティとスピリチュアルの決定的な違い
「スピリチュアリティは『霊性』とも言いますが、フィジカル(体)、メンタル(心)のケアをしてもそれだけではケアしきれない、もっと深いところにある「痛みを感じる奥深い魂」とも言える領域を指す用語です」
「現在ではホスピスにおけるスピリチュアル・ケアなど医療においても使用されています。この形容詞が『スピリチュアル』です」と教えてくれた伊藤さん。
信頼性の高い言葉で言い換えるなら、無意識が一番近いとのこと。「スピリチュアル=目に見えない疑わしいもの」という認識は、活動している団体や発信内容によって大きく異なるそうです。
1.2 スピリチュアリティとの出会いと財団法人の設立
伊藤さんがスピリチュアリティ研究に携わるようになったきっかけは、「スピリチュアル」という言葉が持つ誤解を解くためのカウンセリングの経験でした。
多くの相談者が抱える問題の根底には、心の深い部分での葛藤があることに気付き、それを体系的に研究する必要性を感じたとのこと。
1995年に大学を卒業後、短期間報道機関に勤務し、その後20年間にわたって調査業に従事し、専門機関での研究を終え博士号取得後も、明治以降から続く日本の霊性思想の研究と、フィールドワークによる現状の把握に努めてきました。
これらの情報を発信する機関が必要と考え、2021年9月、一般財団法人 スピリチュアリティ・リサーチセンターの設立に至ったのです。

1.3 スピリチュアリティ・リサーチセンターでの活動内容
伊藤さんの活動は、「研究」、「調査」、「発信」、「対話」、「実践」の5本柱から成っているとのこと。
「研究は、スピリチュアリティに関する既存の文献及び独自の調査から得られたデータを用い、スピリチュアリティの現在について分析を行います。調査は、現地調査及・聞き取り・アンケート等で直接得た情報をデータベース化し、必要に応じて提供しています」
「また、スピリチュアリティに関わる宗教関係者・精神世界関係者・医療関係者などと、市民との対話のためのフォーラムを定期的に行い、その結果を積極的に発信、データベース化しています。査定を行うにあたり、実際に体験が必要なものに関してはワークショップを開催し、スピリチュアリティの在り方を模索しています」
多くの学術機関では学術関係者しか分からない専門的な言い回しで説明がされることが多い中、伊藤さんの財団では、専門家ではなくても分かる言葉で、専門家が話す知識が得られるよう心がけているそうです。
2.伊藤さん独自の身体操作術の魅力
伊藤さんは、古武術を基にした身体操作術のワークショップの運営にも力を入れています。
「参加者には武術に興味がない人も多く、武術と切り離して伝える必要がありますが、それが難しく、初期の受講生の教育にも苦労しました」
身体操作術は、メンタルと体の両方を活用する独自の技術のため、腰やひざなどの関節の負担の軽減に加え、自己肯定感の向上やメンタルヘルス不調にも効果があるとのこと。
オンラインでの伝達が難しいため、対面指導に力を入れており、今後は専属インストラクターの育成や、技術の普及を目指されています。
※下記は立ち合いの動画です
3.志師塾で研究を成果に変えられた
3.1 志師塾に入る前の悩み
「志師塾に入る前は、研究成果をどうコンテンツ化し、どう提供するかに悩んでいました」と伊藤さんは振り返ります。
伊藤さんが志師塾に入塾する前に抱えていた最大の悩みは、自身の研究成果をどのように社会に伝え、実際の価値として提供するかという点です。
スピリチュアリティに関する研究で多くの知識と経験を持ちながらも、その研究が「どのように人々に役立つか」を明確にすることが難しかったとのこと。
加えて、大学の外で研究を続ける際に必要な資金やサポートをどう確保するかも大きな課題でした。
大学院では利用できた研究施設や図書館などのリソースを、在野の立場でどう補完するか、またそれを長期的に維持していくためのビジネスモデルが見えず、行き詰まりを感じていたのです。
3.2 志師塾で得られたもの
伊藤さんが志師塾で得た最大の成果は、自身の研究成果をコンテンツとして提供するための具体的な手段を学べたことです。
自身の研究がどのように社会に受け入れられ、さらに価値として提供できるかを考える力を得られたとのこと。
「単なる論文や研究発表にとどまらず、ワークショップやセミナーなどの具体的なコンテンツに結びつけることができるようになりました」と笑顔で話してくれました。
志師塾での経験は、スピリチュアリティの研究を広く社会に伝えるための重要な転機となったのです。
3.3 志師塾の仲間の魅力
「志師塾のコミュニティは、ただ学びを共有するだけの場ではなく、メンバー同士が互いに支え合い、成長し合うことができます。カウンセラーやコーチ、アーティストなど、さまざまなバックグラウンドを持つ人々が集まり、それぞれが持つ知識や経験を共有しています」
コミュニティの中で、異なる職業や専門性を持つ人々とのディスカッションやフィードバックを通じて、多様な視点を得ることで、自分の考え方を深め、広げることができたとのこと。
特に、同じ問題意識を持つ仲間たちと一緒に課題に取り組むことで、伊藤さんは自身の研究をより実践的に、そして社会的に価値あるものとして形にすることができました。
さらに、同期の仲間は、学びの場を越えて、ビジネスや人生における信頼できるパートナーとなったのです。
3.4 独自サービスで単価アップ、集客を改善をしたい方へ
コンテンツが作れない、価値はあるのに単価が低い、集客が思うようにいかないと感じる方は、「価値の伝え方」を見直すことが大切です。

「重要なのは、自分が提供するサービスやコンテンツがどのように相手にとって役立つかを明確に伝えることです。単に商品やサービスの内容を伝えるだけでは不十分で、それがどのように顧客の課題を解決するか、どんな変化をもたらすかに焦点を当てることで、顧客に真の価値が伝わり、結果として単価アップにもつながります」
伊藤さんと同じように悩んでいる起業家へ、メッセージをいただきました。
「失敗を恐れずに進むことで、必ず何かしらの答えが見つかる。志師塾は、その道を見つけるための一歩を後押ししてくれる場所です」
4.公益財団法人の設立を目指して
最後に伊藤さんの今後の目標をお伺いしました。
「風呂敷を広げてお話しすると、私は公益財団法人を目指しています。できれば、内閣府から認証を受けて公益財団法人として活動したいと思っています。公益財団法人は全国規模で活動できるので、そのスケールで活動を広げていきたいと考えています」
「内閣府から認証を受けると、補助金が取りやすくなり、研究費を引き出すのも容易になります。もちろん、その分、検査や制約も多くなりますが、それでもメリットが大きいです。たとえば、日本最大の公益財団法人は「日本財団」。その次に大きいのが「日本相撲協会」や「日本武道館」といった歴史ある団体です。私は、そういった規模の団体を目指したいと思っています」
理想の未来について語る伊藤さんから、笑みがこぼれます。具体的にどのような財団を運営したいかについてもお伺いしました。
「財団としては、研究員として論文を書いたり、学会に参加して発表したりする人材を20人程度、さらに役員10人を加えて50人体制にしたいと考えています」
「そのメンバーが、財団でしっかりと収入を得ながら、自分のペースで副業も自由に活動できる環境を整えることで、それぞれの専門分野で活躍しつつ、安定した生活を送れるようにしたいと思っています」
伊藤さんに集まる多くの仲間が、自分の能力を最大限に発揮し、やりがいを感じながら仕事ができる環境が実現される未来が楽しみでなりません。

文・編集:志師塾編集部
年商1,000万円以上を目指したい士業・コンサル・講師・コーチ・セラピストなどの先生業の方は、伊藤さんも学んだWebを活用し、高単価で安定的に顧客獲得するためのノウハウを、学んでみてください。