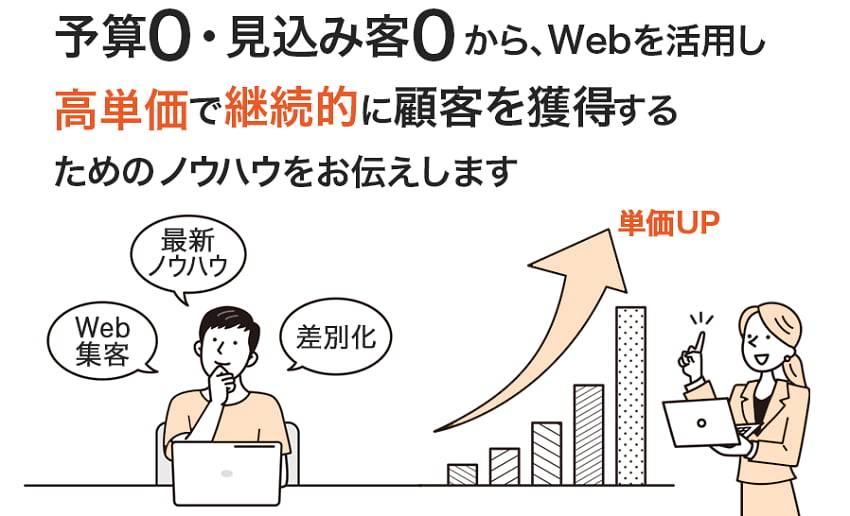今回ご紹介するのは、志師塾卒業生であり、現在は障害年金に特化した社会保険労務士として活躍されている熊岡政道(くまおか・まさみち)さんです。
熊岡さんはもともと、交通関連企業で長年会社員として勤務されていましたが、一念発起して社会保険労務士の資格を取得し、現在の道を歩み始められました。
「知らないことで損をしない世の中にしたい」——そんな想いを胸に、障害年金に特化した社会保険労務士として日々奔走されています。
今回は、熊岡さんが志師塾で得た学びや、今後描いている展望について、お話をうかがいました。
1.社会保険労務士・熊岡さんの現場力
1.1 障害年金に特化した社会保険労務士
横浜市を拠点に活動する社会保険労務士・熊岡政道さん。年金制度の中でも、特に手続きが複雑で繊細な「障害年金」に専門特化して取り組んでいます。
社会保険制度には、「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」の3つがありますが、熊岡さんはその中でも特に障害年金に注力。法律や制度が複雑で、申請者本人では手続きが難しい分野に真正面から取り組み、「少しでも困っている人の助けになりたい」と語ります。
相談のきっかけは、紹介によるものが中心です。障害者施設や病院、特例子会社(障害のある方を積極的に雇用する企業)といった現場からの紹介に加え、同業の社会保険労務士からの依頼もあります。
ホームページ「年金横浜」も運営しており、最近ではWeb経由での相談も増加しているといいます。
「年金分野は専門性が高く、対応できないという社会保険労務士の方からもよく相談をいただきます。そういうときこそ、自分の役割を感じます」
1.2 「断らない」を信条に
障害年金は、制度の複雑さと個別性の高さから、社会保険労務士の業務の中でも特に難易度が高い分野とされています。診断書の記載内容、病歴、日常生活の困難さなど、判断材料が多岐にわたり、画一的な対応が通用しにくい領域でもあります。
それでも熊岡さんは、「原則として依頼を断らない」という信念を貫いています。
「もちろん難しい案件もあります。でも、まずは話を聞いて、そのうえで一緒に考える。最初から断ることはしません」
障害年金を求める方の多くは、生活に不安を抱え、社会とのつながりが希薄になっている場合も少なくありません。そんな中で「相談しても断られた」と感じれば、制度自体への信頼も損なわれてしまいます。
「『頼れるところがなかった』、『ここまで話を聞いてくれたのは初めて』とおっしゃる方もいます。そういう声を聞くたびに、『断らない支援』の意味を改めて実感します」
たとえ受給に至らないケースであっても、相談者の話をじっくりと聞き、状況を丁寧に整理し、一緒に可能性を探る——その積み重ねこそが、熊岡さんの支援の原点です。

2.交通関連会社の会社員から社会保険労務士への転身
2.1 人生の転機となる社会保険労務士の資格取得
「このまま60歳まで過ごすのかと考えたときに、『何かを変えたい』と思ったんです」
転職先で出会った社会保険労務士に影響され、45歳で社会保険労務士資格取得を決意。4度の不合格を乗り越え、5回目で念願の合格。2年後に今の事務所を立ち上げます。実務経験ゼロからの開業でした。
2.2 「年金を極める」と決めた日
熊岡さんの業務は、まず行政の年金相談員として実務経験を積むことから始まりました。年金事務所での相談業務では、行政の判断基準や書類作成の実務を肌で学ぶことができ、今でもその現場感覚が支援の根幹になっているといいます。
この実務経験を通じて「もっと専門性を高めたい」と思うようになり、挑戦したのが「年金アドバイザー検定2級」でした。なんとこの試験で、熊岡さんは全国1位という快挙を達成します。
「そのとき、『年金を極めよう』と腹をくくりました」
その後、着実に経験を重ね、現在では障害者施設や病院、特例子会社などからの紹介で、安定的に相談が寄せられる体制を築いています。
しかし、ここまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。開業当初は実績も紹介もない中、熊岡さんは自ら営業活動を始めます。
「開業当初は、FAXや電話で障害者施設にアプローチしていました。とにかく数をこなすしかないと思って、何百件も送ったこともあります」
地道で泥くさい取り組みの積み重ねこそが、現在の信頼とネットワークを築く礎になったのです。

3.志師塾との出会い
3.1 志師塾へ入塾を決意
志師塾を知ったきっかけは、Facebook。熊岡さんが信頼する社会保険労務士の先生が「いいね」していたことから、なんとなく参加した無料相談会が始まりでした。
「月によって売上に波があり、安定させたいという思いがありました。『今より良くなるかも』という気持ちで入塾しました」
実はその決断が、熊岡さんの大きな転機になったのです。
3.2 志師塾でみつけた「自分の伝え方」
入塾後、まず取り組んだのは「プロフィールページの充実」。これまで書いてこなかった「自分の人生の波」をストーリーとして表現することで、相談者の信頼感が大きく変わったといいます。
「以前は『年金に詳しい社会保険労務士』としてしかみられていなかった。でも、人生の背景を知ったうえで相談されると、相手の安心感が全然違う」
チラシにも自己紹介を加え、名刺にはQRコードを掲載。
「もともと会社員時代に営業も経験していたため、病院や障害者施設への訪問時にはパンフレットを直接置かせてもらうこともあります。受付にそっと置いたチラシから相談が入ることもあり、地道な活動が実を結んでいる実感があります」
会社員時代に蓄積したノウハウも活かしています。

3.3 売上は2倍に。月2件だった受給件数が、今では4~5件に
志師塾で学んだことは、単なる「伝え方」だけにとどまりませんでした。
自分自身の強みを再発見し、継続的な発信につなげたことで、受給件数は月2件から4~5件へ。売上も、受給件数の増加に伴いおよそ2倍に伸びたとのこと。
「もちろん、継続してこそ意味があります。でも、確実に成果は出ていると感じます」
しかし、熊岡さんは、業務の質にもこだわります。
「受給支援は一人ひとりに深く寄り添う仕事なので、1人で対応できるのは月5件程度が限界です。それ以上は質を落としてしまうと感じています」
3.4 仲間と学び、未来を描く
志師塾では、毎回課題があります。日々の業務に追われる中、提出物の締め切りがギリギリになることも。「夏休みの宿題を8月29日から始めるタイプなので(笑)」と、笑顔で話す熊岡さんですが、行動に移す力は誰よりも強かったのです。
志師塾を通じて出会った異業種の仲間たちからも、多くの刺激を受けてきました。今後は合宿や講演家養成講座などにも積極的に参加予定です。
「診断士や税理士の方、士業じゃない方とも出会えるのが魅力ですね。自分とは違う視点からの学びがあります。今後は、そうした異業種の仲間と連携して、障害年金や福祉に関する相談会・啓発セミナーなども共催できればと考えています」
そして、熊岡さんが見据える未来は、さらに大きなステージへと向かいます。
4.未来を見据えた熊岡さんの新たな挑戦
4.1 法人化と支援協会構想に込めた想い
「これまでは個人事業主でしたが、近いうちに法人化する予定です。組織として活動することで、より社会的な信頼性を高めたい」
法人化は単なる形式の変更ではありません。受給者に対して、そして紹介元の施設・医療機関に対して“安心して任せられる事務所”であることを証明するための、重要な一歩です。
次に、熊岡さんは“障害者の障害年金申請を支援する協会”の立ち上げを試みています。単独の事務所では限界がある支援を、志を同じくする社会保険労務士仲間とともに広げていこうとしています。
「病気や障害に悩んでいる方の中には、制度の壁に阻まれて支援が届かないケースも多い。そうした人たちを支える社会インフラが必要です」
特に熊岡さんが注目するのは、“一度不支給になってしまった方”への再支援。制度上、再申請は可能であるにもかかわらず、多くの人が諦めてしまう現状に対して、他の事務所が扱わない難しい案件にも真正面から取り組む姿勢をみせています。
「誰もやりたがらないことに、あえて挑む。それが自分なりの『オリジナリティ』です」

4.2 10年、15年、一生涯をかけて
熊岡さんは、開業後数年してがんを経験されました。現在は幸いにも回復され、再発や転移もなく、日々元気に業務に取り組まれています。この経験は、熊岡さんの中にある“未来につながる支援”をより強く意識させるきっかけとなったといいます。
「がんを経験したことで、支援を必要とする方々の不安が、より身近に感じられるようになりました。だからこそ、制度だけでは支えきれない『心』にも寄り添いたいと思うようになったんです」
こうした想いは、これからの取り組みにも反映されています。
「私がいなくなっても、想いを継いでくれる人がいれば、その支援は社会に残っていく」
その実現に向けて、熊岡さんが掲げるのは組織化と後進の育成です。法人化は単なる形式ではなく、“支援のしくみを自分ひとりのものから、社会全体の財産へと変えていくためのスタート”と語ります。
志を同じくする仲間とともに、永続的に支援が届く社会インフラを築くこと——それが、熊岡さんが10年、15年、そして一生涯をかけて取り組もうとしている未来のかたちです。
インタビューを通じて、ひとつひとつのご相談に丁寧に向き合う誠実な姿勢が印象に残りました。熊岡さんの新たな挑戦は、まさにこれから本格的に動き出そうとしています。
文:植村裕加(中小企業診断士)/編集:志師塾編集部
年商1,000万円以上を目指したい士業・コンサル・講師・コーチ・セラピストなどの先生業の方は、熊岡さんも学んだWebを活用し、高単価で安定的に顧客獲得するためのノウハウを、学んでみてください。